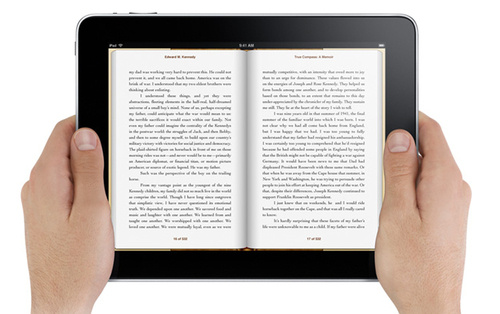
当然電子書籍にはデメリットもあります。それを冷静に見つめる事で、それを克服していけたらいいなと考えています。
作品に偏りがある
まだまだ実験段階という印象が拭えない理由の1つに作品の絶対量が少ないという事があります。
当然想定されているのは紙の書籍の豊富さです。
紙の書籍は日本語にしぼっただけでも何千/何万では全然効かない膨大な量が存在します。
あらゆる言語ということになったら、それこそ想像も尽きません。
しかし電子になっている書籍に数はまだまだ数えられる程にしかありません。
電子書籍だけではまだまだ読みたい物がすべて読めるわけではありません。
ただ、このデメリットは電子書籍全体で見たときには徐々に解消されていくと確信しています。
本当に数が増えたときは紙の様な物理的制約がない電子書籍の方がより多くの書籍が存在するようになると思います。
また、アマチュアが発表するための容易さでは紙とは比較になりません。その点においてもユニークな作品が電子書籍には集まる可能性があると思います。
表現力
今のところ電子書籍閲覧のメインとなるのはパソコンのディスプレーだと思われますが、その表現力はどこをどうあがいても紙に勝るとは思えません。
ただ、T-Timeのようなソフトウェアや電子インクの様な新技術などによりこの問題は徐々にではあっても解決していく問題だと思います。
名称の不統一
この分野は『電子書籍』『電子本』『電子出版』『電子テキスト』『電子ブック』など名称の統一がなされていません。その結果、サーチエンジンなどの検索の際にロスが生じてしまいます。
もっとも、それほどの不都合があるわけでもなく、大きな問題ではないと思います。
存在の不確実性
電子書籍は電子の書籍です。つまり実体がありません。HDD等の中などにデジタル情報として記憶されています。もし記憶されている機械に故障がおきた場合、その電子書籍は2度と読めないかもしれません。
インターネットの世界は移ろいやすい物です。
今日ある物が明日あるという保証が出来ない世界です。
欲しいと思ったものはその場で自分のHDDなどに保存しておかないと作者のウェブサイトにあるからいいやなんて考えていると次の日にはなくなっているかもしれない。
そんなリスクが絶えず存在します。
この事はある程度の数のリンク集を作った事がある人にはすぐに実感出来ることでしょうし、そうでなくても多くの人が実感しているのではないかなと思います。
紙の書籍の場合本屋がなくなっても出版社がなくなったも書籍そのものは無くなりません。
完売もしくは裁断しない限り手に入れる手段はあるでしょう。
しかし、電子書籍の場合は手に入れる手段がなくなってしまう可能性が非常に高いです。
