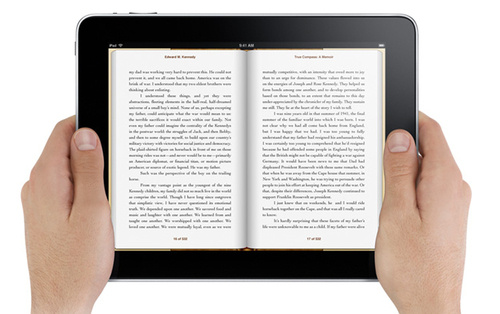
既存物の権利
コンテンツの多くは紙媒体での出版を前提とした契約下で関係者が製作に携わったものであり、その電子化と公開ではそれら関係者の利権がからみあいます。
デジタル情報ゆえに新たな契約が対象とする配布媒体・データ形態の範囲がわかりにくい、コンテンツの電子化にも技術面以外の様々なハードルが存在している。
著作権切れの無料物
プロジェクト・グーテンベルクや青空文庫のような著作権切れコンテンツも存在するが、そういった過去の作品だけでは電子書籍の利用者のニーズを満たせない。
著作権切れの書籍などをデジタル情報による無料コンテンツへ加工する作業は、ボランティアか無償提供目的の公益の事業などが行なっている。
日本では国立国会図書館や複数の大学図書館、美術館などが著作権適用期間を過ぎた古い書物や古文書の電子化を行なっているが、これらは互いに異なるファイル形式で記述しているために、利用者には不便である。
また、逆に商業的な電子書籍の流通網は基本的に使用できないために、閲覧者の利便性を損なう面もある。
大手IT企業の動き
オンライン書店最大手のAmazonや検索サイトのGoogleの2社は、これまで紙媒体で存在するメディアの電子書籍化を大規模に進めている。
Google社は著作権者に無断で電子書籍化を進めてそれらをネットワーク上で公開することで権利を侵害したとして、米国内で著者・出版社団体から訴えられ、2年以上にもわたる係争の結果、多額の和解料の支払いとユーザーに対する課金および著作権料徴収を徹底するという条件を飲むことでようやく和解に至っている。
新聞・出版社などの立場
世界的に日刊新聞の発行部数は下降しており、日本では出版業界も1990年中頃から後半にかけて販売が減少し、これらの電子書籍への参入を後押ししている。
"Wall Street Journal"や"FOX"を保有する米Newsグループでは2009年から2010年に電子書籍への参入するとされる。
"San Francisco Chronicle"や"ESPN"を保有する米Hearstも2009年に電子書籍への参入するとされる。
米最大手の書店"Barnes & Noble"も2009年内に電子書籍販売サイトを立ち上げる。
図書館
公立図書館では、2002年北海道岩見沢市立図書館が電子書籍の閲覧サービスを始めたが、需要が少なかったため、書店の指定した2カ月の無償での試行の後、取り止めとなった。
大学図書館では、紀伊國屋書店が手がけるOCLC[4]の学術教養系和書・洋書の電子書籍配信サービス、ネットライブラリー(NetLibrary)が、早くから普及している。
特に2009年10月、凸版印刷と紀伊國屋書店の協業後、学術教養系和書電子書籍のコンテンツ数が増えている。
