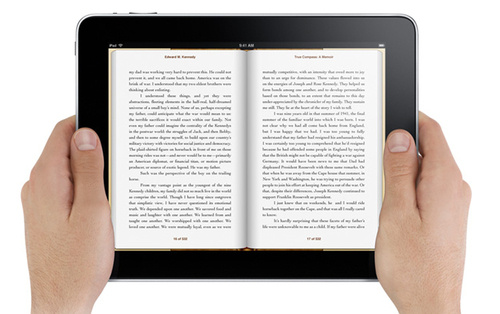
米国では、2012年1月時点で18歳以上人口全体の約2割が「タブレット」端末を保有しており、この勢いは今も続いています。2010年の春に本格投入が始まってから2年も経過していないデジタル製品としては、驚くべき早さで普及が進んでいるといえます。 日本では、タブレット端末に一定の関心を持っている人は多いのですが、まだ利用をためらっている人も多いようです。パソコンやスマートフォンと異なるタブレット端末の役割が、日本ではアメリカほどはっきりと見えてきているようではないようです。そこで、日本とアメリカの違いを見て行きましょう。
日本で普及しない理由
時代の近代化に伴い、読書の形態も変わってまいりました。最近では電子書籍というものが幅を効かせております。
電子書籍とは精密機械を使って本を読むことにあります。
膨大なデーターを電子書籍に取り込むことができるので、たくさんの本を持ち歩く必要がないのです。
手軽に読めるのも電子書籍の魅力であります。
しかし電子書籍はなかなか日本で普及しません。
少しずつ電子書籍の知名度は高まっているのですが、まだまだ発展の余地ありといった感じです。電子書籍が完全に普及するまで時間がかかることが予想されます。
電子書籍が普及しにくい理由の一つに「目が痛くなる」という点が挙げられるでしょう。
直接目に光を浴びせる機械は、目にあまりよくありません。
まだ本を読んだ方が目に優しいのです。パソコンを使用し続けるとドライアイになってしまうように、電子書籍の存在は目に良いとは言い難いものであります
。しかし技術の発達が進み、目に優しい電子書籍が開発されれば今以上に電子書籍は普及することでしょう。
本に対する意識の問題も電子書籍が普及しにくい理由の一つとなります。やはり本といえば紙をめくって読むのが一般的です。
これは一つの文化にもなっているでしょう。紙の方が読みやすいという人も多く存在しており、電子書籍が普及するのは当分先の話かもしれません。
電子書籍のメリットも沢山あるのですが、まだ一般人が電子書籍に慣れていないというのが一番の要因ではないでしょうか。
アメリカの普及状況
アメリカの6〜17歳の子供が電子書籍に接する機会が急速に増えていることが、児童書籍出版のスコラスティック(Scholastic)の調査で分かった。
ただし、電子書籍の読める機械が普及したためで、単純に読書好きが増えたわけではないようだ。
ニューヨーク・タイムズによると、スコラスティックは2006年以降、1年おきに米世帯を対象に読書と識字能力への関心について調査している。
12年8〜9月にハリソン・グループと共同で行った最新調査では、電子書籍を読んだことがある子供の割合は、10年調査と比べてほぼ倍増の46%に達した。
しかし、伝統的に読書への関心が強い女児をみると、頻繁に電子書籍を読む割合が42%から36%に低下した。
デジタル読書経験の増加は、成人と同様に子供の間でもアイパッドなど用途が豊富なタブレット型情報端末が普及している実態を反映しているようだ。
子供のタブレット利用率は、読み取り専用の電子書籍リーダーをわずかに上回っている。
従って、タブレットで本を読むことよりネットワーキングやゲームに夢中になる子供も増えており、スコラスティックのフランシーヌ・アレキサンダー最高学務責任者は「スクリーン・タイム(端末の画面を見る時間)の制限が今の子育ての重要問題になっている」と話した。
一方で、電子書籍を読んだ男児のほぼ25%が「楽しいから本を読んでいる」と答えたほか、年長の子供(9〜17歳)も、50%は「電子書籍が増えればもっと読む」と答えた。
このことから、アメリカでは普及が進んでいることが分かる。日本とは国民性の違いを感じられる一幕である。
