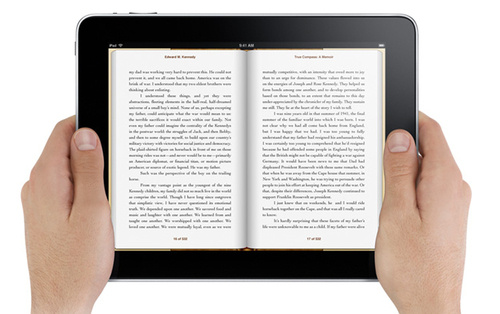
紙の本に比べて、手軽にはなるが電子書籍と閲覧端末が何らかの形で電子機器に依存するため、機器に固有の問題も含んでいる。例えば、電力がなければそもそも利用できないため、発展途上国など停電が常態化している場所や電源が得がたい地域での利用が難しいことなどの問題が挙げられる。
電子書籍は本の全文を試し読みすることができない
Amazonでは目次+αを試し読みできますが,本屋に行けば実物を手にとって全文を読んでから購入を検討できます。
しかし電子書籍ではそれができません。
買うか買わないかを検討するのにはやはり不便です。
電子書籍は「だいたいこのへんを読む」ことができない
電子書籍はページ番号を指定したりスライドすることでページを飛ばしたりできますが,紙の書籍と比べて「このような内容はこの辺に書いてあるはずだからその辺をぱっと開きたい」ということができません。
たとえば,本を買うか決めるときに目次とまえがきとあとがきと著者のプロフィールと目次で気になった箇所をチェックする人はいると思いますが,電子書籍でそれらを紙の書籍と同じスピードでチェックするのはおそらく不可能だろうと思います。
さらに,求める情報の大体のイメージしかないときにそれを探すには本の目次などから推測して「だいたいこのへんかな」と開いてから,開いたページの内容からさらに「ここからこれくらい前/後にありそう」といった推測をして目的の箇所を探しますが,電子書籍ではこれがとてもやりにくいです。
電子書籍は「ざっと読む」ことができない
電子書籍は全ページをざっと読もうとすると,1回1回ページをスライドしていくしかありません。
これで全ページを読むのはとても時間がかかるし,ページの表示にもタイムラグがあるし,何より指が痛いです。
紙の本のようにばーっとページをめくっていくことができないと,概要を把握したり求める情報にたどり着くことができないことが多く,とても不便です。
電子書籍は「自分はどれくらい読んだか」という満足感を得にくい
紙の本だと,読んだページの厚さで自分はどれくらい読んだかがわかります。
そして,たくさん読んでると「あ,もう少しで終わるな」といった満足感を得られます。
しかし電子書籍だと,しおりを挟むことはできるものの,「もう少しで読み終わる」という感覚はあまり持てません。
また,「厚み」という感覚も電子書籍にはあまりありません。
電子書籍は書籍を所有できない
紙の書籍は本棚に置いておくだけで本を所有している感覚を得られますし,実際に「所有」することができます。
すなわち,民法でいうところの「所有権」とは「物を自由に使用収益処分できる権利」であり,紙の書籍は所有することができますが,電子書籍は所有できません。
AmazonにしてもAppleにしても書籍を読む権利をユーザーに与えているだけで,他人に自由に貸したり譲渡したり自分の電子端末に入っている電子書籍で収益をあげたりはできないのです。
そして,電子書籍は紙の本と比べて所有欲が少ないということも指摘できると思います。
電子書籍は紙の書籍の背表紙・表紙・裏表紙から得られる情報を得にくい
紙の書籍は,本棚に並べているだけでも背表紙が見えてそこから書籍と著者の名前,出版社,書籍の大きさ,デザイン,色といった情報を得られます。
この情報は割と便利で,たとえば本について人と話すときに「ああ,あの黄色い本?」とか「こんな感じのデザインのやつ?」といった話ができます。
しかし電子書籍は基本的にぱっとそういった情報が出てこない(電子端末を起動しないとそういった情報を得られない)という問題があります。
